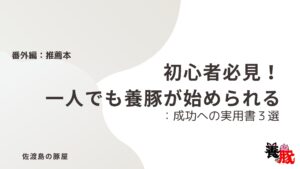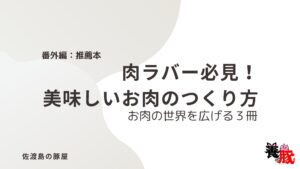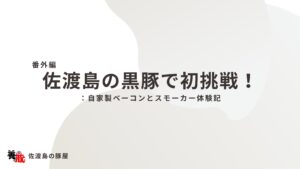「“おいしい”って、どうして感じるんだろう?」
そんな素朴な疑問に、科学的なアプローチで答えてくれるのが『「おいしさ」の科学』という一冊です。
養豚や食品に関わる仕事をしている私にとって、目からウロコの連続でした。
食材の本質、調理技術の裏側まで深く知ることができる内容です。
おいしさとは何か?を科学する
この本は、「おいしさとは何か?」をテーマに、物理・化学・生物学の観点から食材や調理を解き明かしています。
特に私が印象に残ったのは、水の役割に関する話。
なぜ干し椎茸は長持ち? 牛乳はなぜ腐りが早い?
それって水分の量? 水分の状態ってなんなの?
食品の中には「結合水」と「自由水」があり、自由水が少ないと腐りにくくなる(=保存性が上がる)という水分活性と保存性に関わるおはなし。
一方で乾燥が進みすぎると、脂質の酸化が進みやすくなるというデメリットもあるとのこと。
これは、鮭や豚肉の塩漬けもありますよね! 加えたお塩や砂糖に自由水が引き付けられて、自由水の割合が減り結合水の割合が増える! 細菌やカビは結合水では増えない!
では、ジャムは?
イカの塩辛は? めっちゃ気になりますよね?
是非読んでみてください!🙇♂️
肉、魚介、海藻、米まで幅広く解説
『「おいしさ」の科学』では、以下のような内容が取り上げられています:
- 肉の旨味の引き出し方
- 加熱によるわかめの色の変化(緑になる理由)
- アワビの歯ごたえの秘密
- 「強火の遠火」という火加減の理想
- 炭火焼きとおいしさの関係
- 味覚の仕組み
- 「おいしさ」の測定方法や研究
佐渡の食材(ワカメ、アワビ、お米)にも関わりが深いテーマが多く、実生活や仕事にも結びつけやすいです。
調理法の裏側が見えてくる
「強火の遠火」がなぜ理想の火加減なのか?
炭火で焼くとどうして美味しくなるのか?
こうした「感覚的なこと」に科学の裏付けがあるのは、とても学びになります。
お肉を焼くのって難しいんですよね!
私的に、、生すぎてはいけないし、焼きすぎてかたくなっても嫌だし!
料理は技術だけでなく、理論でもうまくなる。
そんなことを改めて感じさせてくれる本でした。🙇♂️
こんな人におすすめ!
- 飲食・食品加工に携わる方
- 調理をもっと深く知りたい方
- 食材の本質や科学に興味がある方
- 「おいしい」の正体を知りたい方
📘 書籍リンク(Amazon)
▶︎ https://amzn.asia/d/6nF7I2j
「おいしさ」を科学的に知ることで、食と向き合う視点が変わる一冊です。
食を扱うすべての方に、ぜひ手に取って読んでいただきたいです。